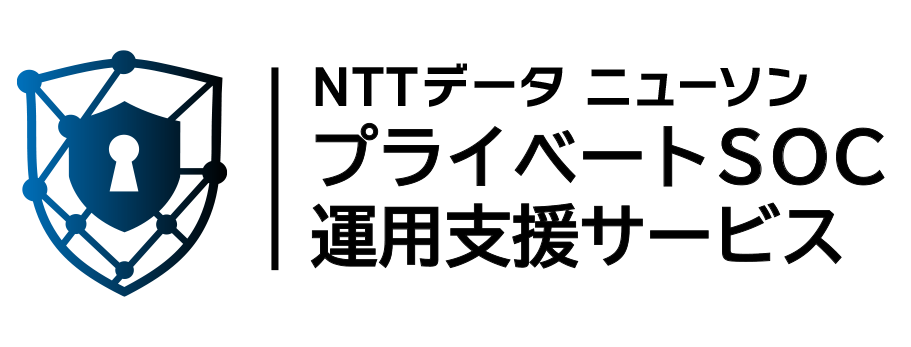ゼロトラストモデルとは?基礎と導入のメリット・デメリットについて
ゼロトラストモデルとは、社外はもちろん、社内からの脅威にもフォーカスし、網羅的にセキュリティ対策を強化する仕組みです。
この記事では、ゼロトラストモデルについて解説します。定義から基本原則、導入するメリット・デメリット、導入が必要な企業の特徴までまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
ゼロトラストモデルとは
ゼロトラストモデルとは、従来のセキュリティモデルである「境界防御モデル」と似て非なる考え方を持つ新たなセキュリティモデルです。そのため、ゼロトラストモデルへの理解を深めるには、まず境界防御モデルについて知る必要があります。
境界防御モデルとは、社内と社外、それぞれの領域に明確な境界線を設けて、「信用できる範囲(社内)」と「信用できない範囲(社外)」を区別することで外部からの攻撃を防ぐセキュリティモデルです。
これに対しゼロトラストモデルは、境界線の概念をなくし、すべてのユーザーや端末を「信用できないもの」と捉え、情報資産やシステムへのアクセス時に脅威ではないかを検証するセキュリティモデルです。
ゼロトラストモデルの基本的な3原則
ここでは、ゼロトラストモデルの根幹となる3原則について解説します。
社内外を問わず、すべての通信を信用しない
ゼロトラストモデルは、社内外を問わずすべてのユーザーや端末によるアクセスを疑い、都度「脅威ではないか」を検証するのが特徴です。ID・パスワードの認証はもちろん、企業による端末承認の有無、アクセス時の位置情報など複数の要素を検証し、アクセスの可否を判断します。これにより、想定外のルートからのマルウェア感染や情報漏えいなどのリスクを回避し、ネットワークの安全性を高めます。
ユーザーや端末には必要最低限の権限のみを付与する
ゼロトラストモデルでは、ユーザーや端末に対し必要最低限の権限のみを付与します。それぞれがタスクや役割を果たすと権限を取り消すのが基本です。これにより、攻撃者によるアクセスを制御しやすくなり、不正アクセスや情報漏えいのリスクを回避できます。
侵害を前提とした設計を行う
ゼロトラストモデルでは、常に情報資産やシステムが攻撃を受ける可能性を考慮します。なぜなら、サイバー攻撃は年々巧妙化・高度化しており、侵害を完全に防ぐことが困難になっているからです。「脅威をリアルタイムで監視するツール」や「端末をサイバー攻撃から守るセキュリティツール」を導入して、異常なアクセスの兆候にいち早く気づき、適切な対処ができる環境づくりが欠かせません。
ゼロトラストモデルを導入するメリット
企業がゼロトラストモデルを導入するメリットは、主に以下の5つです。
セキュリティ対策を強化できる
ゼロトラストモデルの導入により、これまで以上にセキュリティ対策を強化できます。従来の境界防御モデルでは、社内からの脅威には対応しきれませんでしたが、ゼロトラストモデルでは社内を含むすべてのユーザー・端末を疑うため、死角のないセキュリティ対策を実現できます。これにより、不正アクセスや情報漏えいのリスクを大きく低減することが可能です。
リモートワークやクラウド環境でも安全に業務が行える
ゼロトラストモデルでは、社内外を問わずすべてのアクセスに対し、リアルタイムで脅威ではないかを検証します。そのため、リモートワークの実施により従業員が社外からアクセスする場合も、外部パートナーの担当者がクラウドサービスにアクセスする場合も、セキュリティを確保しながら安全に業務が行えます。
コンプライアンス対応を強化できる
ゼロトラストモデルを導入した場合、法令や規制を遵守するために必要な試みを、無駄なく効果的に実現できます。監査ログを収集したりユーザーアクセスのトラッキングしたりすることで、いざというときのコンプライアンスの証明に役立てられます。
IT運用管理の効率化につながる
ゼロトラストモデルでは、社内外を区別せず、すべてのアクセスに対し検証を行うため、シンプルなIT運用管理が可能です。運用の手間を削減できるため、効率化が期待できます。
デジタルトランスフォーメーションの加速を実現できる
上述のとおり、ゼロトラストモデルを導入した場合、リモートワークの実施やクラウドサービスの利用を実現しやすくなります。これらは企業がデジタル技術を活用して競争優位性を確立するうえで必要な要素のため、ゼロトラストモデルを通してデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させることが可能です。
ゼロトラストモデルを導入するデメリット
ゼロトラストモデルを導入することには上述したメリットがある一方で、以下の3つのデメリットもあります。
導入にコストと時間がかかる
ゼロトラストモデルを導入するには、高度なセキュリティソリューションが欠かせません。また、ネットワークを再設計したりデータを暗号化したり、アクセス制御のポリシーを策定したりと、さまざまな準備も必要です。そのため、特に中小企業にとっては、ゼロトラストモデルの導入にかかるコストと時間が大きな負担となることがあります。
このデメリットを回避するには、セキュリティ対策を強化したい領域から段階的にゼロトラストモデルを導入するのがおすすめです。コストと時間を分散できるため、負担を最小限に抑えられます。
ユーザビリティが低下するリスクがある
企業の状況や導入方法によっては、ゼロトラストモデルがユーザビリティを低下させる要因になることがあります。特にいくつもの認証プロセスや継続的な検証が必要になると、ユーザビリティが下がる可能性が考えられます。
このデメリットを回避するには、業務フローを阻害しない設計を考えたり、ID管理ツールや生体認証を活用して認証の手間を減らしたりするのがおすすめです。ユーザビリティへの影響を最小限に抑える方法を十分に検討しましょう。
既存システムとの統合が難しい場合がある
ゼロトラストモデルが必ずしも既存システムと統合できるとは限りません。もし統合できないシステムがある場合は、移行やアップグレードを行う必要があります。
このデメリットを回避するには、あらかじめ既存システムの評価を行うのがおすすめです。ゼロトラストモデルとの適合性を評価し、移行の難易度を見極めることで、対応方針を適切に判断できます。
ゼロトラストモデルの導入が必要な企業の特徴
最後に、ゼロトラストモデルの導入が必要な企業の特徴を解説します。
在宅勤務やリモートワークを積極的に取り入れている企業
在宅勤務やリモートワークを実施している場合、従業員が社外から社内の情報資産やシステムにアクセスすることになります。この状況でもし従業員の端末がマルウェアに感染してしまうと、その端末内にある企業情報はもちろん、自社で管理しているシステムにも危害が及ぶ可能性があります。
こうしたリスクを回避するためには、在宅勤務・リモートワークをしている従業員の端末を常に監視して、セキュリティを強化することが重要です。そのため、ゼロトラストモデルの導入が必要といえます。
クラウドサービスを中心に業務を展開している企業
クラウドサービスのサーバーは社外に置いていることが多く、社内外どこからのアクセスなのか区別しづらい傾向にあります。そのため、従来の境界防御モデルの「社内は信用できる、社外は信用できない」という考え方は通用せず、脆弱性を突かれて不正アクセスや情報漏えいなどの被害を受ける恐れがあります。
こうした背景から、クラウドサービスを中心に業務を展開している企業にこそ、社内外すべてのアクセスに対し検証を行うゼロトラストモデルの導入が必要です。
複数拠点や子会社を管理する大規模組織
管理する端末の多い企業・組織においては、すべての端末のセキュリティレベルを統一し、一括管理するためにゼロトラストモデルの導入が有効です。
エンドポイントセキュリティ(端末レベルでのセキュリティ対策)のソリューションを導入することで、全端末の一括管理が可能となり、アクセス制限の設定やセキュリティパッチの適用が容易に行えるようになります。
まとめ
この記事では、ゼロトラストモデルについて以下の内容を解説しました。
● ゼロトラストモデルとは、すべてのユーザーや端末を「信用できないもの」と捉え、情報資産やシステムへのアクセス時に脅威ではないかを検証するセキュリティモデル
● すべての通信を信用せず、必要最低限の権限のみを付与し、侵害を前提とした設計を行うのが原則
● 企業がゼロトラストモデルを導入した場合「セキュリティ対策・コンプライアンス対応の強化」「IT運用管理の効率化」などのメリットを得られる
● デメリットには「導入にコストと時間がかかる」「ユーザビリティが低下するリスクがある」などがあるが、工夫次第で回避できる
● ゼロトラストモデルの導入は「在宅勤務やリモートワークを積極的に取り入れている」「複数拠点や子会社を管理する大規模組織」などの特徴を持つ企業に向いている
サイバー攻撃が巧妙化・高度化し続けている今、ゼロトラストモデルの導入はセキュリティ対策の強化につながる有効なアプローチです。従来の境界防御モデルでは十分なセキュリティ対策ができないことも多いため、依存せずになるべく早く切り替えることをおすすめします。
ゼロトラストモデルの導入にあたって高度なセキュリティソリューションを取り入れる際は、株式会社NTTデータ ニューソンの『プライベートSOC運用支援サービス』がおすすめです。お客さまの情報システムへの脅威の監視や分析などを行う専門組織である「SOC」の役割を支援するとともに、社内のセキュリティ関連組織である「CSIRT」とも密に連携し、サイバーレジリエンスの実現を図るお手伝いをいたします。この機会にぜひ利用をご検討ください。
『株式会社NTTデータ ニューソン』では、企業内に高度な専門知識がない場合でも確かなセキュリティを担保できるよう、貴社内に構築したプライベートSOC運用を支援するサービスを提供しています。誤検知の判断や優先度づけなど、プロの視点と判断が必要となる領域を、当社のプライベートSOC運用支援サービスが的確に補完します。高度かつ柔軟なセキュリティ対策とコストの最適化を実現が叶うため、この機会にぜひ利用をご検討ください。